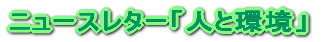
No.3 (2004)
2005.6.16
- P1
- 環境の時代を考える

- P2
- 2003年度環境総研講座
- 2003年度エコフェスタ

- P3
- 現代社会と中世の出会い-圃場整備を前にした中世村落史跡-

- P4
- NPO/NGO団体紹介「NPO生駒いいもり里山サポーターズ」

| OSIES News 人と環境 No.3 p.1 (2004) |
環境の時代を考える
大阪府民環境会議理事・一級建築士事務所主宰 関井 弘之
忘れやすい魂のために、心に物干し台を(日常性と環境問題の行方)
私の大好きなNHK朝ドラ「てるてる家族」が終わってしまい、あの家族と一緒に生きてきた半年間が
何だったのか・・心の中にぽっかりと空洞が出来たみたいだ。(チョットオーバー)
あの家族にはあり、今の一般的家族にはない特別な場所、それが物干し台だ。
記憶では一度も洗濯物が干してある場面を見たことがない。
しかし、あの空間はドラマでは重要な役割を果たしていた。
夫婦がそれぞれの想いを吐露し、溜息をついたり、自分たちの歩んできた道を振り返り、慰めあったり、
子供たちの行く末の幸せを願ったり、子供たちが将来の夢を語り合い、励ましあったり、
一人で自分の気持ちを確認し決意を新たにしている。
それはお茶の間やリビングでの日常会話では話しにくい話である。
そして、そこにはちょっとした非日常の空間がある。
こんな空間を住宅の中に設定する事はそんな難しい事ではない。
ところが何時からか、こんな空間を我々はあまり必要としなくなり、
あまりにも日常性のみの住宅が主流になってしまった。
我々は、本当に日常茶飯の生活にのみに埋没してよいのだろうか?
時には「祈りの空間」にこの身を投げ出し、ひたすら何かを祈り続けたい衝動に駆られる事がないのだろうか?
内なる魂の声に耳を傾ける時間を本当に必要としないのだろうか?
今の自分を見つめ「生きている事の不思議さ」を思う時間を必要としないのだろうか?
本当に願わねばならぬ理想や物事の本来のあり方が何であるかに想いを馳せる事を必要としないのだろうか?
そして、「初心」も「高志」もまた忘れやすく「己の魂」のなんと忘れやすい事か。
また、自分の置かれている環境をすべてアタリマエと考えて、感謝の念もなく、
何も考えず、見ようともしないのはなぜだろうか?
このようなことが環境問題のような日常生活とは一見関係なさそうに見える問題に
想いを廻らす感性を喪失させているとしたら残念な事だ。
我々が生かされている日々の生活の中で水も空気も食べ物もおいしくて当然と思い、
生産性の高さのみを追求する人間社会と、どんなに汚しても浪費しても文句を言わないで黙って守ってくれる大自然。
しかし、残念ながらその大自然の包容力にも限界が来てしまったようである。
ではなぜ、このような問題が起こってしまったのか?
今の社会の底流にどんな発想が横たわっているか、考えてみたくなる。
それは一口で言えば機能主義的自然観ではないだろうか?
産業革命以降、我々は使っている道具や機械と同じように大自然の多様な働きを無視して山や川を一つの役割、
機能としか見なくなった結果であろう。
たとえば、本来、河川の働きは山林の腐葉土から沁み出した水が幾多の渓流や淀みをくぐり抜け
ミネラルたっぷりのおいしい水になり、山を下り海においしい植物プランクトンを生み出す。
また、たくさんの落ち葉が出来る健康な山林は、大雨が降ってもゆっくり大地に浸透し川辺の植物を育て、
少々人間の汚した水でも浄化してゆく。
しかし現代は単に洪水防止という理由だけで、河川改修と称してコンクリートの3面張りの直線コースの
人工河川を造ってしまう。確かに洪水は怖いが洪水の最大原因は森林の保水力の弱さであり、
それは経済的に成り立たなくなった森林管理により森が荒廃したことが一番大きい原因ではないか?
このように単一機能としてのみ川をイメージし、おまけに自然をすべてワカッタツモリでいる事自身が
すべてを表面的利用価値でしか捉えない現代人の機能至上主義そのものであり、
さらに言えば、一つのものの持つ働きを深く色々な角度から見つめようとせず、
自然への畏敬の念を無くしたところに大きな問題があるように思う。
我々は今、少しの余裕と愛の眼差しを持って深く全体的に物事を捉えるべき時期にさしかかっているように思う。
そのためにも、日に一度心の物干し台で星空を眺めもの想うひとときが欲しいものである。
| OSIES News 人と環境 No.3 p.2 (2004) |
2003年度環境総研講座
2003年度大阪信愛女学院短期大学公開講座(城東区、鶴見区共催)の内、
環境総研講座として3回の公開講座を開催しました。
第1回は「環境と健康-環境中の化学物質の危険性-」について国際医薬品臨床開発研究所理事 菊池康基氏に、
第2回は「淀川の水環境を考える-水生生物の視点から-」について環境省希少野生生物種保存推進委員の河合典彦氏に、
第3回は「日本のウミガメと砂浜、そして人間との関わり合い」について日本ウミガメ協議会会長亀崎直樹氏に
ご講演いただきました。
いずれも環境と人間および社会に関わる現代的問題として興味深い内容の講演でした。
第2回と第3回の講演内容については、講演に関連した内容のご寄稿いただき、
本誌前号に掲載いたしておりますので、
ここでは、第1回の講演内容について簡単に振り返ってみることにします。
第1回 環境と健康-環境中の化学物質の危険性-
講師の菊池康基氏は、医薬品の安全性、とくに発がんとの関わりが深い遺伝毒性について、
その重要性をいち早く認識され、試験法の開発、リスク評価など、我が国で先駆的役割を果たされ、
環境変異原学会功労賞を受賞されている。
本講演では、現在、化学物質の危険性について、健康や生態系の破壊等の面で大きな問題となっているが、
正しく認識し、正しく対処する必要があることをわかりやすく話されました。
最初に、生命の進化における環境の関わりの歴史について、とくに環境の毒性的影響とそれに対する
適応の進化について話されました。
有害作用紫外線との戦い(紫外線は遺伝子DNA損傷作用があるが、損傷したDNAを修復する機構を生み出した)、
酸素の毒性と効果的利用の歴史(最初生命は酸素を必要とせず、むしろ強力な毒であった。
しかし、呼吸というエネルギー生産のための酸素を利用する仕組みを備え生命は急激な発展を遂げた)、
化学物質との効果的な関わり(解毒システム、免疫システムの発達)など。
次に、毒の概念と安全についての考え方(100%の安全は存在しない)、
人工化学物質と天然物質の毒性(両者に特別な違いはない)、
薬の効果と副作用について(用い方により薬にも毒にもなる)、
化粧品・食品添加物・農薬・遺伝子組換え植物と危険性(必ずしも正しく認識されていない)、
現代日本における安全性についての一般的な考え方と問題、研究者の責任について話されました。
最後に、変異原性試験のパイオニア、エームス博士による安全に対する一般的な考えの誤りについての提起を紹介され、
寺田寅彦氏の名言「ものをこわがらなすぎたり、こわがりすぎたりするのはやさしいが、
正当にこわがることはなかなかむつかしいことだと思われた」で締めくくられた。
2003年度エコフェスタ
今年度のエコフェスタは、11月8日(土)と9日(日)に、本学の学園祭(楓祭)との同時開催、
学生会楓祭実行委員会との共催で実施しました。
講演会として、園芸療法士の寺田祐美子氏の「心と庭-一鉢から発するユートピア-」、
幼きイエズズ修道会のシスター小井手恵美子氏の「今、私にできること-カンボジアの体験をとおして-」、
NPO法人日本ウミガメ協議会会長の亀先直樹氏の「日本のウミガメと砂浜、そして人間との関わり合い」を開催しました。
また、桂福車さんによる環境落語「食の法則」で楽しみながら環境問題を考えてもらう催しや
元大阪テクノホルティー園芸専門学校教授の太田周作氏によるガーデニング体験講座「癒しの『こけ玉』づくり」、
昨年に引き続き、大阪市環境学習リーダー会による「環境家計簿講座」を実施しました。
パネル展示として「淀川水系イタセンパラ研究会」「日本ウミガメ協議会」「国際ワークキャンプセンター」
「生駒いいもり里山サポーターズ」に参加いただきました。
農民組合大阪府連合会大阪産直センターから安全で新鮮な野菜の直販も昨年に続きありました。
新たな試みとして、(財)千里リサイクルプラザ研究所の市民研究員の方たちが普及・啓発に取り組んでいる
体験型環境学習「イベントのごみゼロ大作戦」を試みました。
同研究員の方たちの実験では、リユース(できるだけ再使用できる食器の使用)とリデュース(食器の持参を呼びかける)
を組み合わせてごみを分別すると、95%以上が資源になる(リサイクル)といわれています。
手順は、①ゴミ箱を撤去、②リサイクルコーナーを設ける、③リサイクルコーナーに机を置き、
その上に回収箱を並べ表示をする、④飲んだり食べたりした人に、自分で分別して回収箱に入れてもらう、
⑤コーナーには必ず担当者が立ち、分別の仕方など、声かけを行う、⑥回収箱が一杯になったら、
担当者が別の袋に移す、⑦分別したものを洗浄し、リサイクルルートにのせる、というものでした。
学生たちと同研究所に行き、直接お話をうかがい、資料をいただき、それらを参考に実施を計画しました。
今回は初めての実施なので、無理のない緩やかな実施ということで試みました。
そのため、①のゴミ箱の撤去を実施せず、リデュースも呼びかけませんでした。
会場入り口に「ごみゼロステーション」を設け、分別回収箱を缶・ペットボトル・食べ残し桶・紙コップ・
トレー・竹串・割り箸・その他燃えるゴミ・その他燃えないゴミの9つに分類し設置し、
当番の学生が交代で協力を呼びかけました。
缶2個、ペットボトル9個、紙コップ148個、紙皿32枚、白いPSPトレー65枚、竹串529本、
割り箸418本(A4用紙約70枚分)の回収ができました。
| OSIES News 人と環境 No.3 p.3 (2004) |
現代社会と中世の出会い-圃場整備を前にした中世村落史跡-
井田 寿邦
今の大阪府泉佐野市大木は、少し離れた土丸も含めて、昔は和泉国日根郡入山田村と呼ばれていました。
これらの地域は、この昔の名前の如く、平野部から山へ入った所にあります。
鎌倉時代の1234年には、平野部の日根野村さらに井原村と鶴原村も加えて、摂政・関白を勤める九条家の荘園となり、
日根荘(ひねのしょう)と呼ばれるようになりました。現在の泉佐野市域の大半にあたります。
南北朝の内乱を経た後の室町時代には、入山田村と日根野村だけが九条家に残され、
さらに時代の推移とともにその維持も困難になっていきました。
そして九条家にとって稀少となったこの荘園を死守するために、1501年4月に前関白九条政基が
京都から大木に移り住んできます。
それは泉佐野市域あたりを舞台に、根来寺方と守護方とが戦闘を繰り返していた時期でもありました。
以来、四年間、彼は入山田村の長福寺に籠もり、支配を立て直すために血道をあげていきます。
そしてその間、彼は日記を書き続けていきます。それは現在、公刊され、『政基公旅引付』とか、
単に『旅引付』とか呼ばれ、また『新修泉佐野市史』のなかの一冊として読み下し文も作られています。
この日記のなかには、九条政基の耳目を通じてですが、戦国時代の実に多様な様相が記されていくことになります。
刻々と変化する当時の政治情勢や軍事情勢などは勿論ですが、特に個々の農民の具体的な立ち居振る舞いが、
また農民群の動きが、地域をめぐる状況の変動とともにリアルタイムで記されていることは極めて貴重で、
全国的にみても唯一の例といえます。さらに大木にかかわる鎌倉時代の日根荘が成立した
当時の田についての記録も残されています。
そして今一つ重要なことは、かつての入山田村の地域が最近まで大規模な「開発」の波を受けておらず、
今に至るまで連綿と農林業の営みが続けられ、昔からの村の景観などを持ち伝えてきていることです。
もちろん今、私達が目にする景観は、鎌倉時代や戦国時代の景観ではなく現在の景観です。
しかし今ある景観のなかに、たとえば500年ほど前の人々の生活や信仰、笑いや涙、雄叫び、
呻き、喘ぎなどをうかがい知ることができるわけです。
たとえば外部の軍勢の侵入に備えて村の若衆が警戒した谷筋とか、通過する軍勢が駐屯して
いる辺りなどを知ることはできますし、また軍勢の侵入を前に激しく鐘が打ち鳴らされた
円満寺や西光寺、蓮華寺、あるいは雨乞いの儀式を行い、また軍勢の陣取りを前に入山田村
のおとな衆が会合を持った火走神社は村の方々の信仰に守られて今もあります。
村の主だった人々が寄り集まって九条政基に対しての対策を講じたであろう毘沙門堂もあります。
また大雨で灌漑用の樋が流され、村の人々は上之郷や長滝など、下流の村の人々の協力を得て
その曳きあげをはかっていますが、どこから流れたのか、その樋のかかっていた箇所もわかってきています。
そして、現在、行われている水利作業などとあわせると、当時の田の広がりを推測することもできます。
家々の所在もかなり絞り込むことができています。
さらに飢饉の有様、夜盗の出現を前にして若衆の夜警と犯人の追尾、等々、村の中での出来事を今ある景観のなかに
ダブらせることもできます。
すなわち現在の大木は、今ある景観のなかに中世と呼ばれた時代の人々の生き様が具体的に、
それぞれの場所を特定しながら汗や涙、笑いなどとともに感じ、また探ることのできる景観を抱えているわけです。
言ってみれば今ある大木の村落景観全体のなかで、いわば現在の日本の一つの原点を具体的に知りうる
全国唯一の地域ということになります。
だからこそ日本で初めて日根荘遺跡として国史跡の指定をうけたものと思います。
ただし現行の法律内では幾つかの地点を指定するという形が取られ、
大木では円満寺・火走神社・毘沙門堂・蓮華寺・香積寺跡が国史跡として指定を受けています。
ところが現在、この大木地域を対象に「農村振興総合整備事業」が計画されています。
農村振興総合整備事業とは、大木地区では生産基盤の整備、平たく言えば「圃場整備」です。
国史跡のある地域で圃場整備の計画とは少し奇異な感じもしますが、これが現実です。
この計画の背景には大木が抱えている農業従事者の高齢化と兼業化、若者の農業離れ、
農地の荒廃という問題があります。
また農業を維持していくためには機械化に対応していくことも必要です。
そして現在、市が描いている圃場整備は、今ある田の区画や用水路をなくし、
新たな田の区画や水路網と道を作り出す土木工事です。
ただそこには大木の将来の農業のあり方、新たな村づくりがみえてきません。
将来の農業のあり方、村づくりがみえないまま大木で「農村振興総合整備事業」がなされても
農業従事者の高齢化と兼業化、若者の農業離れ、農地の荒廃という問題はそのまま残され、
一方では昔をイメージできる、全国的にみても希有な景観は永久に失われてしまうことになります。
現状ではその危惧を払拭することはできません。
中世を彷彿とさせる村落景観を積極的に生かしてこそ大木の新しい村づくりができるのではないか、
と私は提案しています。どのような道を選択するか、「中世」に出会った現代社会が問われているようです。
(泉佐野の歴史と今を知る会事務局長・大阪府立泉南高等学校教諭)
| OSIES News 人と環境 No.3 p.4 (2004) |
環境保全活動を行うNPO・NGOやボランティア団体を紹介するコーナー
若い力と国際協力で、都市近郊の森林を守る「NPO 生駒いいもり里山サポーターズ」
ここ10年ほど前から森林ボランティア活動あるいは里山保全活動がブームである。
そして今では、公益性をもったアウトドアのレジャーの一つとしても確立されたと言えるような状況でもある。
しかし、まだ、時おりハイカーや近隣住民から、自然破壊者として叱られることがある。
確かに、大勢の人間が、カマ・ノコ・ナタあるいはチェーンソーまで持ち出して、
住宅地のすぐ近くの山林で木を切り倒し始めれば、開発で緑を失ってきた私たちには
自然破壊と映っても仕方がないかもしれない。
この、私たちの住まいの近くに残された山林は、多くの場合、農家経営と一体になり
薪炭林・用材林・水源林として、あるいは肥料採取・食材採取・信仰や娯楽に利用されてきた「里山」である。
しかし、ガス・石油などへのエネルギー源の転換、家庭用品や農具などのプラスチックや金属化、
また化学肥料の普及や「米」の減反政策などによる営農意欲の減退などにより、
管理放棄による密林化が進行している。
そして緑に飢えた私たちはその密林化した山林を自然の復活と誤解しているのである。
放置された里山は、常緑樹に覆われた暗い林床となる。あるいはササの密生、竹林の拡大などによって、
他の植物が侵入できなくなり、種の組成が単純化する。
このような中で、少し前ならよく見かけていた身近な生き物や草花が、いま、姿を消していっているのである。
草を刈ったり、木を伐ることによって、植物の多様性が維持され、その多様性に支えられて生き物も
多様であったのである。
そればかりでなく、林床に草が育たない薄暗い山は土壌の浸食がすすみ、土砂崩れなどの防災上や
水源のかん養といった面でも管理作業が必要なのである。
さて、今回紹介する「生駒いいもり里山サポーターズ」(以下、「里山サポーターズ」)
は、そんな観点から生駒の森林を守るために設立された団体である。
「里山サポーターズ」は、生駒山系内の飯盛山(大東市)の山麓にある約66,000㎡の
山林(学校法人大阪信愛女学院所有「大阪信愛女学院観察の森」)を里山保全活動実習地としている団体である。
その前身は、学生たちに自然にふれる機会を増やしたいと考えていた教職員の有志と地域住民によって
1996年の秋に活動を始めた「飯盛・北条の里山を保全する会」である。
初めの5年ほどは実習地内のササ刈りと間伐を中心とした林床整備に追われていたが、
その作業もひと段落したところで、この活動をさらに発展させるため、
2003年2月に名称変更し、同年6月にNPOの認証受けた。現在、約30名が活動している。
会員は50~60歳代が中心であるが、もちろん大阪信愛女学院短期大学の卒業生・在学生などの
若い参加者も何人かいる。
活動内容は、①里山管理作業、②自然環境教育活動、③普及啓発活動などである。
①としては、毎月第一日曜日を例会活動日として上記の山林で、草刈り・枝打ち・
除間伐・道整備・炭焼きなどを実施、
②としては、小学生を対象とした自然観察やクラフト、あるいは一般市民を対象とした
野草料理・野草茶・野草ジャムづくりのイベントなど、
③としては、日本国際ワークキャンプセンター(NICE)との共催で、国内外からの若者の参加のもと
国際ワークキャンプの実施(本紙No,1参照)、また各種イベントに展示出展、さらに今年は、
実習地の植物の紹介などをした冊子の発行、
それに地元大東市民を主な対象とした『里山の楽しみ方教室』(全6回)の開催などを予定している。
このような活動を通して、(社)大阪自然環境保全協会をはじめ、
同じ生駒山系で活動する他の里山保全団体などとの連携をとりながら、
さらに大阪府や大東市がすすめる生駒山系グリーンベルト整備事業などにも積極的に協力し、
自然保護だけでなく防災面でもすぐれた森林づくりをしていこうと考えている。
(大阪信愛女学院短期大学 足高壱夫 記)
![]()